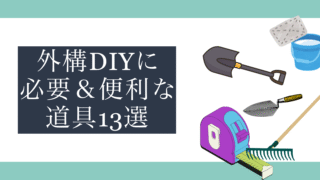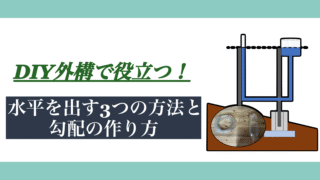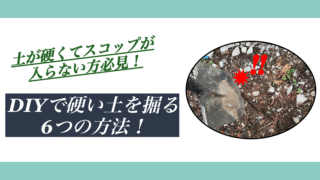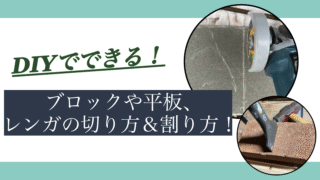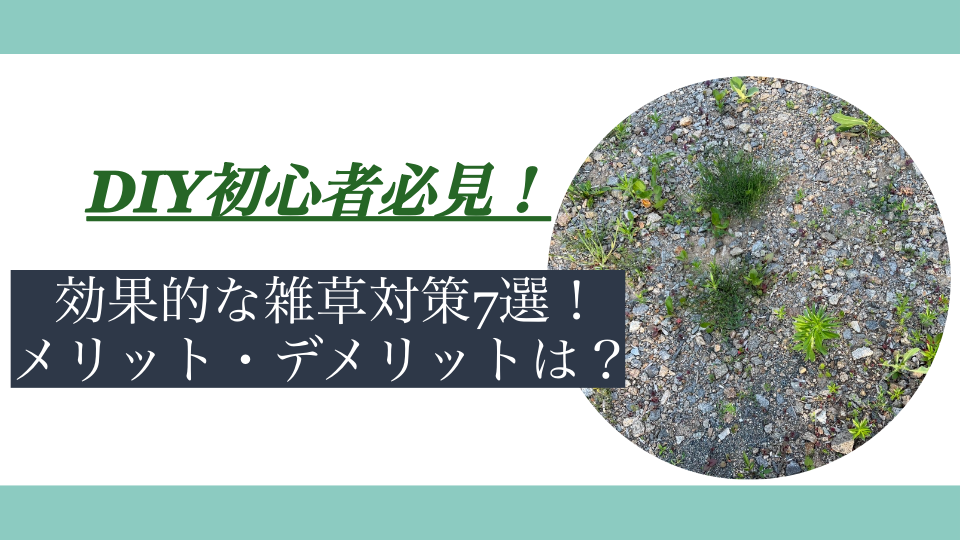庭や玄関アプローチをおしゃれにしたいけど、業者に頼むとコストが高い…。そんなときにおすすめなのが、DIYでできる平板舗装です。
見た目も美しく、使い方次第でナチュラル・モダン・和風など、さまざまな雰囲気に仕上げることができます。
この記事では、DIY初心者の方でもわかりやすいように、基礎づくりから平板の敷設・仕上げまでの手順を詳しく解説します。
平板舗装とは?インターロッキングとの違い
平板舗装とは?

「平板舗装」とは、四角形や長方形の平らな板(コンクリート平板や天然石など)をモルタルやバサモルなどの上に敷き並べて固定する方法です。ホームセンターで手に入るコンクリート製の平板が一般的で、サイズは30cm角や40cm角などがあります。
見た目がシンプルで、モダンな住宅にもナチュラルな庭にも合わせやすく、「雑草対策」や「泥はね防止」としても人気があります。
インターロッキングとの違い

モルタルやバサモルなどで固定する平板舗装に対して、インターロッキングブロックは砂の上に置き、互いに組み合うように敷き詰める舗装方法となっています。
DIYで平板舗装を作る前の準備
必要な道具・資材一覧

今回メインとなる平板は、北海道にあるよねざわ工業さんの「ST平板 450」という商品を使用しました。
その他の道具に関して「いまいちどんな道具かわからない」という方は、外構DIYにおける必要・便利な道具を解説した下記記事を参考にしてみてください。
施工場所の選び方と注意点
1. 地盤の状態を確認する
- 柔らかすぎる地面や水はけが悪い場所は避けるか、しっかりとした下地づくり(砕石・転圧)が必要です。
- 傾斜が急すぎる場所では、平板がズレたり、水たまりができる原因になります。
2. 雑草が多い・日陰は対策が必要
- 雑草が生えやすい場所では、防草シートをしっかり施工すること。
- 日陰は湿気が溜まりやすく、コケが発生しやすいので、滑り止め加工された平板を選ぶと安心です。
施工前に確認しておくポイント
1. 水勾配を確保する
- 水が溜まらないように勾配をつける
- 目安:1mにつき1~2cmの勾配
- 例えば、5mのアプローチなら最低でも5〜10cmの高低差が必要です。
- 勾配は排水方向に向ける
2. 排水経路を確認する
- 雨が降ったときに、水がどこに流れるかを事前に確認。
- すでにある排水マスや側溝へスムーズに流れるような設計にしましょう。
- 平板や目地砂で既存の排水マスをふさがないよう、カットやスペース確保が必要です。
平板舗装の施工手順

今回は基礎に砕石を入れ、1%の勾配をつけた平板舗装のやり方を解説していきます。
STEP1|施工範囲を決めてマーキングする
施工したい場所の形状(四角形・曲線など)を決め、ロープやスプレー、水糸などで範囲を可視化します。
この時、実際のサイズより10〜20cm程度広めに掘っておくと、のちのち作業がしやすくなります。
STEP2|床掘りする

平板の厚さ、砂層、砕石層などを見込んで合計20cm程度掘ります。
寒冷地の場合は、凍害対策として凍結深度まで掘っておくことをおすすめしますが、DIYではかなりしんどい作業になりますので、多少は妥協しても良いかと思います。

私も本来は60㎝ほど掘りたかったですが、30〜40cmで妥協しています。
掘りすぎる分には砕石で調整できるため問題ありません。
また、水勾配を意識して(傾斜をつけて)掘っておきます。(1mで1~2cmの高低差)
DIYで余った土の捨て方や有効利用についてはこちら。
STEP3|転圧して防草シートを敷く

掘った地面を転圧していきます。
足で踏むなどの代用はできますが、範囲が結構広いためタンパーがあると効率的に転圧できます。

砕石を敷いてからも再度転圧するため、体力的にもタンパーかもしくは、プレートコンパクター(転圧機)のレンタルがおすすめですよ!
転圧を終えたら全体に防草シートを敷き、雑草対策を行っておきましょう。
目地を砂で仕上げる場合は、隙間から雑草が生えてくる可能性があるため、防草シートは敷いておいた方が良いですよ。
ちなみにおすすめの防草シートは”ザバーン 240G”という種類で、しぶとい雑草にも効果があり、イタドリやスギナなどのしぶとい雑草も防いでくれています。
また、耐用年数も長く、砂利下など紫外線が当たらない場所であれば半永久的に効果を維持してくれるため、しっかり雑草を抑えたい方にはおすすめとなっています。
| 厚さ | 0.64mm |
| 雑草の種類 | スギナ、チガヤ、ヨシ、笹などの強い雑草 |
| 耐用年数 | 7〜13年(紫外線が当たらない場合半永久) |
STEP4|砕石を敷いて転圧する

- 砕石を5~10cmの厚みで均一に敷き、しっかり転圧(プレートコンパクターまたは手動タンパー)
- 寒冷地の方は、掘った深さに応じて砕石を敷きます。
- 平らさと勾配の確認もしっかり行う。
転圧不足は沈下の原因になりますので、数回に分けて丁寧に圧をかけてあげましょう。
STEP5|外側の平板を並べていく

平板を並べていく前に、まず水糸を張って高さの基準を視覚化します。
そして、この水糸に合わせながら平板をモルタルで固定して並べていきます。モルタルを使用することで平板をずれてしまうの防いでくれます。
モルタルは鏝を使って2〜3cm程度の厚みで敷き、水平器や水糸を見ながらゴムハンマーなどで平板を叩いて高さ調整します。

また、平板同士をピッタリくっつけるようにしながら並べていっても良いですが、目地にセメント類や荒目の砂を入れる場合には、スペーサーを用意して目地幅を確保しておきます。
スペーサーを使用することで、全体の目地幅が揃い、綺麗な平板舗装に仕上がります。
STEP6|内側の平板を並べていく

内側の平板は、バサモル(水が少ないモルタル)を敷いてから並べていきます。
バサモルを使用すると、平板がしっかり固定されるため、施工後に不陸(凸凹)が発生しにくくなるのが大きなメリットです。
今回、私が使用した平板は透水性が高いタイプだったため、凍害リスクを考慮し、急遽「砂」で施工しました。
寒冷地の場合や、透水性の高い平板を使用する場合は、基礎に水を溜めないように注意が必要です。
一方で、凍害リスクのない地域や、浸透しない(透水性の低い)平板を使う場合は、バサモルで施工したほうが安定しやすくおすすめです。
また、平板の加工が必要な場合は、ディスクグラインダーを使うと綺麗に切断することができます。
STEP7|目地に砂を入れる

平板を並べたら、目地の隙間にセメント類や砂などの目地材を詰めていきます。
目地材を入れることで、平板がズレずに固定されますので、目地は必ず入れるようにしましょう。
施工方法は平板の材質や目地材の種類によって異なります。
砂を入れる場合
砂などの目地材であれば、まいた砂をほうきで掃き入れ、最後に水で締め固めるだけなので、比較的簡単にできます。
ただし、目地が固まるわけではないため、施工後に砂が雨などで流れたり、雑草生えてきたりするリスクもあります。
ちなみに砂の種類は、珪砂という細かい砂がよく使われています。
セメント類を入れる場合

一方セメント類の目地を使う場合には、タイルデッキ施工のように鏝で目地材を詰め、最後にスポンジで拭き取る方法などがあります。
しかし、普通はセメント汚れがつきにくい素材にやるやり方なので、素材によってはセメント類が付着すると汚れが取れなくなってしまう場合があります。
今回私が使用した透水性があってザラザラした表面の平板には向いていませんでしたが、目地を詰めてすぐに拭き取れば汚れがつかなかったため、上記画像のような方法で施工しました。

タイルとは違いなるべく汚れないように詰めていくため、結構手間と時間がかかりました。
STEP8|清掃して完成!

目地材を詰めたら、最後にほうきで砂や土を払い、必要に応じて水で綺麗に清掃してあげましょう。
清掃が終われば、完成となります。
中央部分には、焚き火やBBQができるファイヤーピットを作りましたので、こちらのDIY方法についても知りたい方は下記記事を参考にしてみてください。
日差し対策でより快適に!

庭に降り注ぐ夏の日差しはかなり暑く、庭時間の快適さを大きく左右します。
場合によっては熱中症にもなりかねないため、日差し対策は重要になってきます。
詳しい方法については、シェードやパラソルなど8つの対策を紹介した下記記事を参考にしてみてください。

庭に日陰を作るだけで快適さは大きく変わりますよ!
ソーラーライトで夜もおしゃれに演出

平板のアプローチやテラスにソーラーライトを取り入れれば、夜でも美しくライトアップされた空間を楽しめます。
電気工事は不要で、設置も簡単。太陽光で充電するため、電気代がかからず、ランニングコストゼロで使い続けられるのも魅力です。
デザインや種類も豊富で、モダンからアンティーク調までさまざま。平板の色や形、周りの植栽に合わせてライトを選べば、昼間とは違った雰囲気を演出できます。
まとめ
平板舗装のDIYを成功させるためには、基礎をしっかり作ることが最も重要なポイントです。基礎が甘いと、施工後に平板が沈んだりズレたりしてしまい、せっかくのおしゃれな舗装も台無しになってしまいます。
特に寒冷地では凍害対策が必須です。具体的には、凍結深度まで砕石をしっかり敷き、透水性のない平板や目地を使用することが効果的です。これにより、基礎に水が溜まりにくくなり、凍結による浮き上がりやひび割れを防ぐことができます。
正しい手順で丁寧に施工すれば、DIYでも長持ちする平板舗装が実現できます。しっかり基礎を作って、おしゃれで丈夫な庭を目指しましょう!