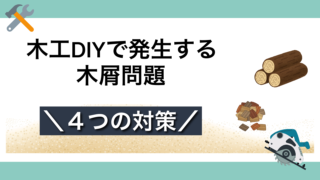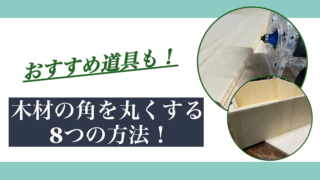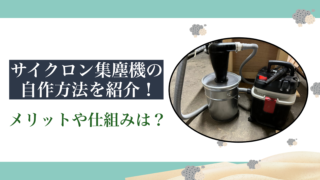DIYで木材を使うとき、「やすり掛けって本当に必要?」と思う方も多いのではないでしょうか。
実はこのひと手間で、仕上がりの見た目も手触りも大きく変わります。
この記事では、木材のやすり掛けが必要な理由から、初心者でも失敗しないやり方、おすすめの道具やペーパーの選び方まで詳しく解説します。
これから木工や外構DIYを始めたい方にもわかりやすくまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
木材のやすり掛けが必要な4つの理由

①表面を美しく滑らかに仕上がるため
やすり掛けを行う最大の目的は、木材の表面を滑らかに整えることです。
製材された木材は一見きれいに見えても、実際には細かな凹凸や繊維の毛羽立ちが残っています。そのまま使うと触り心地がざらついたり、塗装したときにムラができたりする原因になります。
やすり掛けをして表面を整えることで、光沢のあるなめらかな仕上がりになるため、家具や棚板など、見た目を重視したDIYでは欠かせない工程です。
②塗装やニスの密着をよくするため
木材の表面が粗いままだと、塗料が均一に乗らず、ムラや気泡ができやすくなります。
やすり掛けによって表面をほどよく整えると、塗料やニスがしっかり密着し、色ムラのない美しい仕上がりになります。
特にオイルフィニッシュやステイン塗装を行う場合、塗装前のやすり掛けが仕上がりを大きく左右します。
③トゲ・ささくれを防ぐため
木材の切断面や角には、肉眼では見えにくいトゲやささくれが残っていることがあります。
そのまま扱うと手や指に刺さってケガをすることもあり、特にお子さんが触れる家具やペット用品を作る場合は危険です。
やすり掛けをして角を軽く面取り(角を落とす)しておくと、安全で扱いやすい木材になります。
④寸法の微調整にも役立つ
やすり掛けは仕上げだけでなく、寸法の微調整にも役立ちます。
木材をカットしたあと、「あと1〜2mm小さくしたい」といった場面がありますよね。
そんなとき、やすりで少しずつ削ることで正確に調整できます。
ノコギリでは難しい細かな修正もやすり掛けなら簡単なため、DIYでは、精度を上げるための調整作業としても重要な工程です。
やすり掛けの基本手順とコツ
手順1.やすりを掛ける前の準備

やすり掛けを始める前に、まずは木材の状態をしっかり確認しましょう。
表面に大きな傷や割れがある場合は、パテなどで先に補修しておき、その上で研磨すると仕上がりがきれいになります。
手順2.木材を固定する

次に、作業中に木材が動かないようにしっかり固定することが大切です。
クランプや万力を使って固定しておくと、手を痛めず安全にやすり掛けができます。
また、粉じんが出るため、マスクと保護メガネの着用もおすすめです。特に屋内作業では換気も忘れずに行いましょう。
手順3.木目に沿ってやすりを動かすのが基本

やすりを掛けるときは、必ず木目の方向に沿って動かすのが基本です。
木目を無視して横方向にこすると、細かい傷が入り、塗装したときに線が目立ってしまうことがあります。
力を入れすぎず、均一に動かすのがポイント。
角や端の部分は木が欠けやすいので、力を抜いて軽く仕上げるときれいに整います。
木目に沿ったやすり掛けを意識するだけで、仕上がりの質が大きく変わります。
コツ①:番手を変えて段階的に仕上げる
やすりには「#60」「#120」「#240」などの番手(ばんて)があり、数字が小さいほど粗く削れ、大きいほど細かく仕上がります。
DIYでの基本的な流れは、
粗目(#80〜#120) → 中目(#180〜#240) → 細目(#320〜#400)
のように、粗い番手から細かい番手へと段階的に変えていくことです。
最初に大きな凹凸を取り、徐々に表面を整えていくと、ツルツルで滑らかな仕上がりになります。
途中で番手を飛ばすとキズが残りやすいため、2〜3段階で仕上げるのがおすすめです。
コツ②:やすり掛け後は粉をきれいに拭き取る
やすり掛けが終わったら、木材の表面に残った粉(木粉)をきれいに拭き取ることを忘れないようにしましょう。
この粉が残っていると、塗料やニスがしっかり密着せず、ムラや剥がれの原因になります。
乾いた布やブロワーで全体を払い、最後に湿らせた布で軽く拭くとより効果的です。
濡れた状態で塗装するのはNGなので、拭いたあとはしっかり乾かしてから次の工程に進みましょう。
サンドペーパーの番手ごとの特徴と使い分け
⚫︎荒目(#40〜#100)
最も削る力が強く、木材の形を整えたいときや大きく削りたいときに使う番手です。
凹凸の多い板を平らにしたり、角を丸く加工したり、古い塗装を落とすときなどに便利です。
また、表面をあえて荒らして古材風の質感を出したいDIYにもよく使われます。
ただし削りすぎると傷が目立ちやすいので、仕上げ前には中目以上で整えるのがポイントです。
⚫︎中目(#120〜#240)
荒目で整えた木材を、さらに滑らかに仕上げるために使う番手です。
木工作業では、塗装前の下地づくりや最終仕上げにも使われることが多く、最も出番の多い万能タイプといえます。
木材だけでなく、金属のサビや焦げ落としにも対応できるため、DIY初心者はこの番手を中心に揃えておくと便利です。
⚫︎細目(#280〜#400)
塗装やニスを塗る前の最終調整(下地仕上げ)に適した番手です。
この段階で表面を整えることで、塗料がムラなく均一にのり、剥がれにくくなります。
特に硬めの木材では、細目で丁寧に磨くだけでもすべすべとした自然な仕上がりになり、無塗装でも美しい質感を出せます。
⚫︎極細目(#400〜#800)
主に塗装の合間に使う仕上げ用の番手です。
一度塗った塗料の刷毛跡を軽く削ったり、2度塗り前の下地を整えるときに使用します。
オイルステイン仕上げなどでは、塗料と一緒に研磨する「ウェット研磨」にも使われます。
ただし、木材の研磨としては細かすぎるため、最終仕上げ程度にとどめましょう。
⚫︎超極細目(#1000〜#2000)
木材というよりは、金属や石、硬質素材のツヤ出しや仕上げに使う番手です。
サビ取りや鏡面仕上げに向いており、傷を消してピカピカに磨き上げたいときに最適です。
DIYでは、金具・工具・塗装面のメンテナンスなどに活用できます。
⚫︎超精密研磨(#2000以上)
#2000を超える番手は、もはや「削る」というより磨き上げるためのペーパーです。
精密機器の部品や貴金属、プラスチック模型などのキズ取り・光沢出しに使われます。
木材では出番はほとんどありませんが、仕上げの美観にこだわるプロ用の領域といえます。
このように、サンドペーパーは番手によって削る力も仕上がりも大きく変わるため、用途に合わせて使い分けることが大切です。
DIY初心者の方は「荒目・中目・細目」の3種類を揃えておくと、ほとんどの作業に対応できます。
DIYにおすすめの研磨道具
やすり掛けは紙やすりだけでも行えますが、広い面や数が多い場合はかなりの労力がかかります。
そんなときに役立つのが、サンダーやサンディングブロックです。
◾️当て木(サンディングブロック)

紙やすりを平らな木片などに巻き付けて使うことで、力が均一に伝わり、面を平らに仕上げやすくなります。
ペーパーのみの作業に比べて格段に精度や効率が上がり、角や細部の整えにも便利です。
◾️サンダー(電動やすり)

モーターでやすり部分を振動・回転させる電動工具で、短時間で効率よく研磨できるのがサンダーの魅力です。
特にランダムサンダーやオービタルサンダーは木工DIYとの相性が良く、ムラのない滑らかな仕上がりが得られます。
フェンスやデッキなど、大量の木材を研磨する作業では必須アイテムといってもいいでしょう。
また、集じん機能付きタイプを選べば、粉の飛散を抑えて室内でも快適に作業できます。

個人的にはランダムサンダーの方が研磨力が高く、仕上げも綺麗にできるためおすすめです!
◾️集塵機

やすり掛けは意外と大量の木粉や粉塵が発生する作業です。
そのため、作業中の粉塵対策と作業後の掃除がとても大切になります。
特に電動サンダーを使う場合は、集じん機(掃除機)を接続しておくと便利です。
研磨中に木粉を吸い込みながら作業できるため、空気中に粉塵が舞いにくく、作業環境を清潔に保てます。
また、作業後に残った木屑や粉塵をしっかり吸引して片付けることで、次の作業がスムーズになるだけでなく、呼吸器への影響や火災リスクの軽減にもつながります。
DIYを安全に楽しむためにも、粉塵対策はしっかり行いましょう。
仕上がりをワンランク上げるポイントと注意点
◾️塗装やオイル仕上げ前に確認すべきポイント
前述しましたが、やすり掛けを終えたら木粉が残っていないかをしっかり確認しましょう。
表面に粉が残っていると、塗料のノリが悪くムラの原因になります。
◾️角や細部の仕上げはスポンジやすりが便利
平面はサンドペーパーで十分ですが、角や曲面・細かい部分はスポンジやすりが便利です。
スポンジの柔軟性で木の形にフィットしやすく、仕上がりも自然になります。
◾️屋外用木材は防腐塗料前のやすり掛けが重要
デッキ材やフェンス材などの屋外で使う木材は、塗料を塗る前のやすり掛けが特に大切です。
表面の汚れや油分を落とすことで、防腐塗料の浸透性が高まり、耐久性が長持ちします。
新材でも軽く研磨してから塗ることで、塗料の密着がぐっと良くなります。
まとめ|やすり掛けでDIYの完成度が大きく変わる
やすり掛けは一見地味な作業ですが、仕上がりの美しさや塗装の質を左右する重要な工程です。
丁寧に研磨することで、木材の手触りやツヤが増し、作品の完成度がぐっと上がります。
初心者でも、木目に沿って段階的にやすりを掛ける・粉をしっかり拭き取るなど、基本を押さえればきれいに仕上がりますよ。